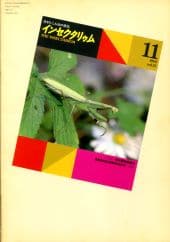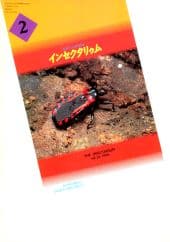| 巻 |
月 |
通巻No. |
発行年 |
特集・記事など(一部抜粋) |
価格
(日本円) |
| 1 |
5月 |
5 |
1964 |
|
¥100 |
| 2 |
1月 |
13 |
1965 |
|
¥100 |
| 2 |
2月 |
14 |
1965 |
|
¥100 |
| 2 |
3月 |
15 |
1965 |
|
¥100 |
| 2 |
4月 |
16 |
1965 |
|
¥100 |
| 2 |
5月 |
17 |
1965 |
|
¥100 |
| 2 |
6月 |
18 |
1965 |
|
¥100 |
| 2 |
8月 |
20 |
1965 |
|
¥100 |
| 2 |
9月 |
21 |
1965 |
|
¥100 |
| 2 |
10月 |
22 |
1965 |
|
¥100 |
| 2 |
11月 |
23 |
1965 |
|
¥100 |
| 2 |
12月 |
24 |
1965 |
|
¥100 |
| 3 |
1月 |
25 |
1966 |
|
¥100 |
| 3 |
2月 |
26 |
1966 |
|
¥100 |
| 3 |
4月 |
28 |
1966 |
|
¥100 |
| 3 |
6月 |
30 |
1966 |
|
¥100 |
| 3 |
9月 |
33 |
1966 |
|
¥100 |
| 3 |
10月 |
34 |
1966 |
|
¥100 |
| 3 |
11月 |
35 |
1966 |
|
¥100 |
| 3 |
12月 |
36 |
1966 |
|
¥100 |
| 4 |
1月 |
37 |
1967 |
|
¥100 |
| 4 |
10月 |
46 |
1967 |
磐瀬太郎:肉食のチョウ幼虫(2ページ) |
¥100 |
| 5 |
5月 |
53 |
1968 |
多摩動物公園昆虫園本館開館記年号 |
¥100 |
| 5 |
6月 |
54 |
1968 |
常木勝次:ジガバチの生活 |
¥100 |
| 5 |
9月 |
57 |
1968 |
松浦寛子:ガの幼虫採集 |
¥100 |
| 5 |
11月 |
59 |
1968 |
五十嵐 邁:遠征採集の技術、黒沢良彦:小笠原諸島の昆虫 |
¥100 |
| 5 |
12月 |
60 |
1968 |
青木淳一:土の中のダニ |
¥100 |
| 6 |
4月 |
64 |
1969 |
|
¥100 |
| 6 |
6月 |
66 |
1969 |
|
¥100 |
| 6 |
11月 |
71 |
1969 |
|
¥100 |
| 6 |
12月 |
72 |
1969 |
黒佐和義・黒沢良彦・田中和夫・林 長閑・三宅義一ほか:座談会 甲虫飼育の楽しさ |
¥100 |
| 7 |
1月 |
73 |
1970 |
林 長閑:クワガタムシの飼育(4ページ) |
¥100 |
| 7 |
2月 |
74 |
1970 |
枝 重夫:北アメリカのトンボを追って(4ページ) |
¥100 |
| 7 |
3月 |
75 |
1970 |
高倉忠博:タテハ類の飼育(4ページ) |
¥100 |
| 7 |
4月 |
76 |
1970 |
三枝博幸:カマキリ類の飼育と観察(4ページ) |
¥100 |
| 7 |
5月 |
77 |
1970 |
座談会:磐瀬太郎先生をしのぶ(4ページ)、磐瀬太郎先生年譜・インセクタリゥム掲載記事リスト(計1ページ) |
¥100 |
| 7 |
6月 |
78 |
1970 |
守本陸也:アシナガバチの飼い方(4ページ) |
¥100 |
| 7 |
7月 |
79 |
1970 |
大野正男:ハムシの生態(1)エサとその食べかた(4ページ) |
¥100 |
| 7 |
8月 |
80 |
1970 |
板倉 博:富士山頂で見られた昆虫と飛来時の気象(4ページ) |
¥100 |
| 7 |
9月 |
81 |
1970 |
編集部:ホタルの現状について-アンケート調査から-(6ページ) |
¥100 |
| 7 |
10月 |
82 |
1970 |
|
¥100 |
| 7 |
11月 |
83 |
1970 |
大平仁夫:コメツキムシ幼虫の飼育(4ページ) |
¥100 |
| 7 |
12月 |
84 |
1970 |
茂木正邦:ヘイケボタルの飼育(1)(4ページ) |
¥100 |
| 8 |
1月 |
85 |
1971 |
小林森巳:ハナアブの生活 |
¥100 |
| 8 |
2月 |
86 |
1971 |
本藤 昇:ナガサキアゲハを飼う、1970年度総目次(別紙付録)
|
¥100 |
| 8 |
3月 |
87 |
1971 |
|
¥100 |
| 8 |
4月 |
88 |
1971 |
奥谷禎一:ハバチ類の飼い方 |
¥100 |
| 8 |
5月 |
89 |
1971 |
|
¥100 |
| 8 |
6月 |
90 |
1971 |
|
¥100 |
| 8 |
7月 |
91 |
1971 |
服部伊楚子:ドクガ類の幼虫を飼う |
¥100 |
| 8 |
8月 |
92 |
1971 |
上島法博:トコジラミの生態 |
¥100 |
| 8 |
10月 |
94 |
1971 |
|
¥100 |
| 8 |
11月 |
95 |
1971 |
野淵 輝:キクイムシの生活 |
¥100 |
| 8 |
12月 |
96 |
1971 |
小林俊樹:ベニモンオオサシガメを飼う |
¥100 |
| 9 |
1月 |
97 |
1972 |
河合省三:オオワラジカイガラムシの生態 |
¥100 |
| 9 |
2月 |
98 |
1972 |
北野日出男:ヤドリバチの生態 |
¥100 |
| 9 |
3月 |
99 |
1972 |
内藤 篤:アワフキムシの生活 |
¥100 |
| 9 |
5月 |
101 |
1972 |
佐藤正孝:ヒラタドロムシの生活 |
¥100 |
| 9 |
7月 |
103 |
1972 |
久保田政雄:アリの飼育 |
¥100 |
| 9 |
8月 |
104 |
1972 |
|
¥100 |
| 9 |
9月 |
105 |
1972 |
|
¥100 |
| 9 |
10月 |
106 |
1972 |
桝田 長:日本産タマバチの生活 |
¥100 |
| 10 |
1月 |
109 |
1973 |
萱嶋 泉:クモの飼育法、松田達郎:南極の虫 |
¥100 |
| 10 |
3月 |
111 |
1973 |
藤山家徳:大むかしの昆虫たち |
¥100 |
| 10 |
4月 |
112 |
1973 |
井上 巌:ハリガネムシの生活 |
¥100 |
| 10 |
6月 |
114 |
1973 |
南部敏明:ジガバチモドキの飼い方 |
¥100 |
| 10 |
7月 |
115 |
1973 |
照屋 匡:沖縄の侵入昆虫-バナナセセリについて- |
¥100 |
| 10 |
8月 |
116 |
1973 |
大川親雄:耳へはいる昆虫 |
¥100 |
| 10 |
9月 |
117 |
1973 |
久松定成:ケシキスイの生活 |
¥100 |
| 10 |
12月 |
120 |
1973 |
小島圭三:カミキリムシ類の飼育 |
¥100 |
| 11 |
1月 |
121 |
1974 |
井上智雄:わらまきによる昆虫の観察 |
¥100 |
| 11 |
3月 |
123 |
1974 |
宮沢 謙ほか:テントウムシの集団遺伝、宮本正一:水生昆虫の呼吸 |
¥100 |
| 11 |
7月 |
127 |
1974 |
松本忠夫:熱帯のシロアリ、千葉喜彦:蚊柱 |
¥100 |
| 11 |
8月 |
128 |
1974 |
上野俊一:洞窟にすんでいる昆虫、林 正美:変わった習性をもつセミ |
¥100 |
| 11 |
9月 |
129 |
1974 |
嶌 洪:ヤドリバエの生活、岩田久二雄:ハチは恐くない |
¥100 |
| 11 |
10月 |
130 |
1974 |
立川周二:カメムシ類の親の配慮 その保護習性、渡辺賢一:トンボの連結について |
¥100 |
| 11 |
11月 |
131 |
1974 |
近藤正樹:アリの道、三枝豊平:ミノガの配偶行動 |
¥100 |
| 11 |
12月 |
132 |
1974 |
森川国康:カニムシの生態、千葉喜彦:昆虫の日周活動、1974年度総目次 |
¥100 |
| 12 |
2月 |
134 |
1975 |
小林比佐雄:ハムシの生活史、ハリクチブトカメムシの食性 |
¥100 |
| 12 |
3月 |
135 |
1975 |
小原嘉明:翅の謎-モンシロチョウ- |
¥100 |
| 12 |
6月 |
138 |
1975 |
市川俊英:トビイロウンカの配偶行動、川島恂二:眼の障害と昆虫、津田正夫:ファーブル巡礼記①生村訪問 |
¥100 |
| 12 |
9月 |
141 |
1975 |
生方秀紀:カラカネトンボの縄ばり行動 |
¥100 |
| 12 |
11月 |
143 |
1975 |
カマキリ特集号
松良俊明:カマキリの生活、山崎柄根:カマキリのプロフィール、久田光彦:カマキリの捕食攻撃、井上民二:カマキリの種内関係 |
¥200 |
| 12 |
12月 |
144 |
1975 |
新島渓子:トビムシ類の生態、1975年度総目次 |
¥100 |
| 13 |
3月 |
147 |
1976 |
阪口浩平:ノミの生態から |
¥100 |
| 13 |
9月 |
153 |
1976 |
ハチ特集号
坂上昭一:南米にひろがったアフリカミツバチ、山根爽一:台湾にホソアシナガバチを追って、片山栄助:マルハナバチ類の産卵と育児、前田泰生:野生ハナバチの利用、石川良輔:ハチ
進化の道すじ、岩田久二雄:渇水の島の昆虫 |
¥300 |
| 13 |
10月 |
154 |
1976 |
奥井一満:シリアゲムシの配偶行動 |
¥100 |
| 13 |
12月 |
156 |
1976 |
福田晴夫:クロシジミの生活-アリと共棲する幼虫-、谷岸一紀:ナミテントウの越冬、1976年度総目次 |
¥100 |
| 14 |
3月 |
159 |
1977 |
岩田久二雄:ミズバチの生活、伊藤嘉昭:昆虫生態学の基礎③ |
¥100 |
| 14 |
6月 |
162 |
1977 |
稲垣典宏(小6):カバフドロバチの観察、兼久勝夫:ゴミムシ類の出すにおいについて |
¥100 |
| 14 |
12月 |
168 |
1977 |
近藤正樹:アリの越冬、1977年度総目次 |
¥100 |
| 15 |
3月 |
171 |
1978 |
友国雅章:グンバイムシの生活 |
¥100 |
| 15 |
4月 |
172 |
1978 |
青木重幸:兵隊をもったアブラムシ |
¥100 |
| 15 |
6月 |
174 |
1978 |
特集:ホタル
堀 道雄ほか:ゲンジボタル成虫の野外個体群 京都市清滝川での状況と方法(8ページ)、矢島 稔:ホタルの日周活動性と光の信号 ゲンジボタルの場合(8ページ)、荻野
昭:昆虫園におけるホタルの飼育(7ページ)、出口吉昭:ホタルの棲む水(4ページ)、大場信義:ヒメボタルの生活(5ページ)、小西正泰・清水 孝:神田左京
ホタルに魅せられた男の光跡(6ページ)、佐藤正孝:日本のホタル(6ページ)、矢島 稔:和名の由来(2ページ)、ほか |
¥500 |
| 15 |
8月 |
176 |
1978 |
高倉忠博:自然保護とチョウ類 失地回復の方策② |
¥100 |
| 15 |
10月 |
178 |
1978 |
稲垣 新:たそがれ時に飛び交うヤンマたち |
¥100 |
| 15 |
11月 |
179 |
1978 |
佐々木陽一:オオハキリバチの交尾行動、八木沼健夫:クモを知るために④クモとすみか |
¥100 |
| 15 |
12月 |
180 |
1978 |
本多計一:アゲハチョウの蛹の色は何で決まるか、八木沼健夫:クモを知るために⑤クモと網、1978年度総目次 |
¥100 |
| 16 |
2月 |
182 |
1979 |
巣瀬 司:ササウオタマバエの長期休眠、八木沼健夫:クモを知るために⑥クモと食物 |
¥100 |
| 16 |
4月 |
184 |
1979 |
大谷 剛:ミツバチのオスを追跡する、八木沼健夫:クモを知るために⑦クモの親子 |
¥100 |
| 16 |
5月 |
185 |
1979 |
吉田利男:ヘビトンボの生活 幼虫を中心に、八木沼健夫:クモを知るために⑧クモと敵 |
¥100 |
| 16 |
6月 |
186 |
1979 |
中村茂子:衣類につく虫、石井象二郎:私とゴキブリ |
¥100 |
| 16 |
9月 |
189 |
1979 |
常喜 豊:ミノウスバ幼虫の護身術、相良直彦ほか:クロスズメバチの巣跡からキノコ、大串龍一:流水の昆虫学②水生昆虫と生態学の源流 |
¥100 |
| 17 |
2月 |
194 |
1980 |
日高敏隆:昆虫にはなぜ色がついているのか |
¥100 |
| 17 |
6月 |
198 |
1980 |
渡辺 守:ナミアゲハの生態学②ナミアゲハの生命表、関口晃一:クモを知るために⑪クモの成長 |
¥100 |
| 17 |
7月 |
199 |
1980 |
渡辺 守:ナミアゲハの生態学③おいしい餌とまずい餌 |
¥100 |
| 巻 |
月 |
通巻No. |
発行年 |
特集・記事など(一部抜粋) |
価格
(日本円) |
| 17 |
12月 |
204 |
1980 |
松浦 誠:社会性カリバチの越冬、林 正美:伊豆諸島のセミ、林 長閑:家屋内のシバンムシ類、1980年度総目次 |
¥100 |
| 18 |
1月 |
205 |
1981 |
梅谷献二:マメゾウムシの生物学①マメゾウムシの仲間たち、ブルース・タバシュニク(訳:伊藤嘉昭):アメリカのモンキチョウ-なぜ一部の種だけが害虫化したか? |
¥100 |
| 18 |
6月 |
210 |
1981 |
上宮健吉:ヨシノメバエの生活、梅谷献二:マメゾウムシの生物学⑥インゲンマメゾウムシの歩く1齢幼虫 |
¥100 |
| 18 |
9月 |
213 |
1981 |
上宮健吉:ヨシノメバエの配偶行動(I)、梅谷献二:マメゾウムシの生物学⑨原野から畑へ |
¥100 |
| 18 |
11月 |
215 |
1981 |
梅鉢幸重:昆虫の体色、梅谷献二:マメゾウムシの生物学【付録】アズキゾウムシの飼い方 |
¥100 |
| 18 |
12月 |
216 |
1981 |
滝沢春雄:ハムシ科の生活様式、早川博文:フン虫を利用した放牧草地のクリーン作戦、1981年度総目次 |
¥100 |
| 19 |
1月 |
217 |
1982 |
日高敏隆:昆虫の触角(5ページ)、佐々治寛之:テントウムシ類の食性1(6ページ) |
¥100 |
| 19 |
2月 |
218 |
1982 |
佐々治寛之:テントウムシ類の食性2(5ページ)、南部敏明:ジガバチモドキの生活から 習性観察のすすめ(6ページ) |
¥100 |
| 19 |
3月 |
219 |
1982 |
長島孝行:ガロアムシの生活史(6ページ)、尾形洋一:マークオサムシの観察(4ページ)、佐々治寛之:テントウムシ類の食性3(5ページ) |
¥100 |
| 19 |
4月 |
220 |
1982 |
宮田保:トモエガの生活(6ページ)、下沢楯夫:昆虫の聴覚(7ページ) |
¥100 |
| 19 |
7月 |
223 |
1982 |
田中 誠:虫送り(9ページ) |
¥100 |
| 19 |
8月 |
224 |
1982 |
渡辺信敬:ガムシ類の形態と習性(6ページ) |
¥100 |
| 19 |
9月 |
225 |
1982 |
林幸治:アメンボの生態(6ページ)、所沢市立宮前小学校昆虫クラブ:コハンミョウのなぞを探る(4ページ)、青木 良:オトシブミ類の形態と産卵行動(6ページ) |
¥100 |
| 19 |
10月 |
226 |
1982 |
木本浩之:カマキリのディスプレイ(8ページ)、竹中英雄:ツツハムシ類の生活(5ページ) |
¥100 |
| 19 |
11月 |
227 |
1982 |
大串龍一:スマトラの自然と虫と1(5ページ)、加納康嗣ほか:ササキリモドキ類の配偶行動(4ページ)、巣瀬 司ほか:ヤマトイソユスリカの生態(7ページ) |
¥100 |
| 20 |
1月 |
229 |
1983 |
宇尾淳子:蛹とは何か1(6ページ)、中田正彦:刀剣美術と昆虫(4ページ)、松浦 誠:社会性ハチ類の生態1(7ページ) |
¥100 |
| 20 |
2月 |
230 |
1983 |
宇尾淳子:蛹とは何か2(7ページ)、松浦 誠:社会性ハチ類の生態2(8ページ) |
¥100 |
| 20 |
3月 |
231 |
1983 |
岩城 操:ヌマカの生活 鰓で呼吸する幼虫と蛹(4ページ)、山根爽一:スマトラの自然と虫と3(7ページ)、松浦 誠:社会性ハチ類の生態3(6ページ) |
¥100 |
| 20 |
4月 |
232 |
1983 |
市川憲平:タガメの交尾産卵行動(4ページ)、松浦 誠:社会性ハチ類の生態4(6ページ)、田中 寛:日本のトノサマバッタ 密度の効果を調べる1(5ページ) |
¥100 |
| 20 |
5月 |
233 |
1983 |
松浦 誠:スマトラの自然と虫と4 熱帯のスズメバチとミツバチ(6ページ)、田中 寛:日本のトノサマバッタ 密度の効果を調べる2(10ページ) |
¥100 |
| 20 |
6月 |
234 |
1983 |
渡辺泰明:ハネカクシという名の昆虫(5ページ)、松浦誠:社会性ハチ類の生態5(6ページ) |
¥100 |
| 20 |
7月 |
235 |
1983 |
松浦 誠:社会性ハチ類の生態6(6ページ)、坂上昭一:スマトラの自然と虫と5(12ページ) |
¥100 |
| 20 |
9月 |
237 |
1983 |
桐谷圭治:移住する昆虫1(9ページ)、松浦 誠:社会性ハチ類の生態8(7ページ) |
¥100 |
| 20 |
10月 |
238 |
1983 |
林 長閑:甲虫の幼虫たちの足とくらし(4ページ)、桐谷圭治:移住する昆虫2(8ページ) |
¥100 |
| 20 |
11月 |
239 |
1983 |
山本 優:ユスリカの生活(4ページ)、桐谷圭治:移住する昆虫3(8ページ) |
¥100 |
| 20 |
12月 |
240 |
1983 |
窪木幹夫:シロスジカミキリの生活(6ページ)、桐谷圭治:移住する昆虫4(10ページ)、1983年度総目次 |
¥100 |
| 21 |
1月 |
241 |
1984 |
大場信義:お正月に飛ぶホタル オオシママドボタル(7ページ)、平野千里:昆虫のおしっこ(7ページ)、 |
¥100 |
| 21 |
2月 |
242 |
1984 |
矢野宏二:ヤチバエの生活(4ページ)、高橋真弓:ジャノメチョウ類の産卵(4ページ) |
¥100 |
| 21 |
3月 |
243 |
1984 |
市川憲平:ゲンゴロウの飼育から(3ページ)、大原賢二:ベッコウハナアブ類の生活(6ページ) |
¥100 |
| 21 |
4月 |
244 |
1984 |
浜崎詔三郎:桜とアブラムシ(5ページ)、松浦 誠:社会性ハチ類の生態9(6ページ) |
¥100 |
| 21 |
5月 |
245 |
1984 |
伊藤富子:筒巣をつくるトビケラ 特にカクツツトビケラについて(8ページ)、松浦 誠:社会性ハチ類の生態10(7ページ) |
¥100 |
| 21 |
6月 |
246 |
1984 |
桐谷圭治:移住する昆虫5(8ページ)、松浦 誠:社会性ハチ類の生態11(7ページ) |
¥100 |
| 21 |
7月 |
247 |
1984 |
巣瀬 司ほか:産卵様式から見たムラサキツバメの生態(7ページ)、田中 誠:ホタルが変えた暦(3ページ)、桐谷圭治:移住する昆虫6(8ページ)、松浦 誠:社会性ハチ類の生態12(7ページ) |
¥100 |
| 21 |
9月 |
249 |
1984 |
石井 実:蝶の吸水行動の謎(8ページ)、松浦 誠:社会性ハチ類の生態14(7ページ) |
¥100 |
| 21 |
10月 |
250 |
1984 |
富樫一次:クリの木をめぐる虫たち(5ページ)、桐谷圭治:移住する昆虫8(9ページ)、松浦 誠:社会性ハチ類の生態15(6ページ) |
¥100 |
| 21 |
11月 |
251 |
1984 |
窪木幹夫:センノカミキリの配偶行動(7ページ)、松浦 誠:社会性ハチ類の生態16(最終回)(9ページ)、桐谷圭治:移住する昆虫9(最終回)(10ページ) |
¥100 |
| 21 |
12月 |
252 |
1984 |
佐々治寛之:テントウムシダマシ類の生活(4ページ)、幸島司郎:氷河に生きる昆虫を求めて(10ページ)、1984年度総目次 |
¥100 |
| 22 |
12月 |
264 |
1985 |
岡田一次:ミツバチの蜂球(7ページ)、酒井春彦:雌アリの新巣建設(4ページ)、内田臣一:川虫のすみかとくらし 自然観察入門(7ページ)、1985年度総目次 |
¥100 |
| 24 |
1月 |
277 |
1987 |
斎藤 裕:ハダニの社会行動1(7ページ)、長谷川 仁:障子紙に巣食う虫たち 忘れられた虫のいたずら(4ページ) |
¥100 |
| 24 |
2月 |
278 |
1987 |
桐谷圭治・田中 章:馬毛島で大発生したトノサマバッタ(11ページ)、酒井春彦:アリスアブの飼育から(3ページ)、ハダニの社会行動2(6ページ) |
¥100 |
| 24 |
3月 |
279 |
1987 |
ピアス ナオミ・伊藤嘉昭(訳):シジミチョウとアリ 寄生から相利共生まで(8ページ)、岡田俊典ヒナカマキリの飼育から(4ページ) |
¥100 |
| 24 |
4月 |
280 |
1987 |
守屋成一:アカスジキンカメムシの飼育 ダイズ・ラッカセイによる累代飼育(6ページ) |
¥100 |
| 24 |
5月 |
281 |
1987 |
松村 雄:ヤマトアブの滞飛行動(7ページ) |
¥100 |
| 24 |
6月 |
282 |
1987 |
石井 実:鱗翅類の変わった食性(8ページ)、森 豊彦:地衣類を採食するシロアリの生態(6ページ)、谷口育英:ヒメカマキリの飼育から(2ページ) |
¥100 |
| 24 |
7月 |
283 |
1987 |
井上 弘:ヨコヅナサシガメの生態(6ページ)、保賀昭雄:オオセンチコガネとセンチコガネの生活(5ページ) |
¥100 |
| 24 |
10月 |
286 |
1987 |
安藤喜一:キリギリスの生物学(5ページ) |
¥100 |
| 25 |
1月 |
289 |
1988 |
M.T.シバジョシー(訳:辻 和希):カブトムシのオスの二型と交尾戦術 ※日本産カブトムシ |
¥100 |
| 25 |
2月 |
290 |
1988 |
唐沢安美:オオルリオサムシの飼育観察から①、松香宏隆:南の島のホタルの木、前田泰生ほか:但馬 楽音寺のウツギノヒメハナバチ |
¥100 |
| 25 |
3月 |
291 |
1988 |
唐沢安美:オオルリオサムシの飼育観察から②、酒井春彦:羽アリは巣の創設後何年目に現れるか |
¥100 |
| 25 |
4月 |
292 |
1988 |
戒能洋一:カイロモンとは何か |
¥100 |
| 25 |
6月 |
294 |
1988 |
特集:昆虫生態園オープン |
¥100 |
| 25 |
7月 |
295 |
1988 |
内藤親彦:ハバチ類の食性と種分化II |
¥100 |
| 25 |
9月 |
297 |
1988 |
増子恵一:ムカシアリの生態II、渡辺 守ほか:アマゴイルリトンボの生活 |
¥100 |
| 25 |
11月 |
299 |
1988 |
堀 浩二ほか:野鳥の巣とトリキンバエ類の生活-シジュウカラ・ニュウナイスズメ・コムクドリなど- |
¥100 |
| 25 |
12月 |
300 |
1988 |
斉藤一三:ブユの生活と飼育、酒井春彦:アリ類の結婚飛行の条件、1988年度総目次 |
¥100 |
| 巻 |
月 |
通巻No. |
発行年 |
特集・記事など(一部抜粋) |
価格
(日本円) |
| 27 |
1月 |
313 |
1990 |
桜谷保之:ナナホシテントウの越冬と越夏、梅谷献二:ラッキーグラスホッパーズ 創られたバッタたち、上田恭一郎:シーボルトの標本と日本の昆虫学1、小西正泰:虫・人・本1松村松年 |
¥100 |
| 27 |
2月 |
314 |
1990 |
大原昌宏:エンマムシの生息環境と形態の多様性、西川正明:チビシデムシの生活、上田恭一郎:シーボルトの標本と日本の昆虫学2、小西正泰:虫・人・本2名和靖 |
¥100 |
| 27 |
3月 |
315 |
1990 |
上田恭一郎:シーボルトの標本と日本の昆虫学3、小西正泰:虫・人・本3三宅恒方 |
¥100 |
| 27 |
8月 |
320 |
1990 |
木船悌嗣・前田泰生:ネジレバネ類の生態5、小西正泰:虫・人・本8高橋 奨 |
¥100 |
| 27 |
9月 |
321 |
1990 |
田中誠二:コオロギ類の長翅型と短翅型、横井直人:キボシカミキリの配偶行動と精子置換、小西正泰:虫・人・本9大町文衛 |
¥100 |
| 27 |
10月 |
322 |
1990 |
田辺 力:ヤスデのくらし・色・かたち、梅谷献二:釣りエサの商虫たち1、小西正泰:虫・人・本10平山修次郎 |
¥100 |
| 27 |
11月 |
323 |
1990 |
桜井宏紀:ナナホシテントウの休眠のしくみ、中川隆志:チョウの大編隊 移動するアフリカのシロチョウ、梅谷献二:釣りエサの商虫たち2、小西正泰:虫・人・本11加藤正世 |
¥100 |
| 27 |
12月 |
324 |
1990 |
渡辺 仁:昆虫の病気、小西正泰:虫・人・本12小山内 龍、1990年度総目次 |
¥100 |
| 28 |
1月 |
325 |
1991 |
内田臣一:カワゲラの分布と水温 多摩川を例として、小西正泰:虫・人・本13 |
¥100 |
| 28 |
2月 |
326 |
1991 |
岡田 茂:ツマベニチョウの飼育、上田恭一郎:昆虫化石 採集調査の現場から、小西正泰:虫・人・本14 |
¥100 |
| 28 |
3月 |
327 |
1991 |
林 正美(文)・佐藤有恒(写真):アワフキムシの生活、三枝豊平・山根正気:沿海州の昆虫と自然I、小西正泰:虫・人・本15 |
¥100 |
| 28 |
4月 |
328 |
1991 |
岩田隆太郎:オオトラカミキリの生態-これまでに分かったこと-(6ページ)、小西正泰:虫・人・本16 |
¥200 |
| 28 |
5月 |
329 |
1991 |
山根爽一:巣をかみきってコロニーを増やすオーストラリアのチビアシナガバチ、市川憲平:タガメの繁殖戦略、小西正泰:虫・人・本17 |
¥200 |
| 28 |
6月 |
330 |
1991 |
巣瀬 司:タケツノアブラムシの兵個体は何を守っているのか、佐々木健志:ナガマルコガネグモの交尾行動と性的共喰い、小西正泰:虫・人・本18 |
¥100 |
| 28 |
7月 |
331 |
1991 |
桐谷圭治:地球の温暖化は昆虫にどんな影響を与えるか、小西正泰:虫・人・本19 |
¥100 |
| 28 |
8月 |
332 |
1991 |
東 昭:昆虫の飛行、小西正泰:虫・人・本20 |
¥100 |
| 28 |
10月 |
334 |
1991 |
堀尾政博:竹の節に産卵するスリランカのオオカ、井上 健:ランの花粉媒介者としてのガ、小西正泰:虫・人・本22 |
¥100 |
| 28 |
11月 |
335 |
1991 |
田中一裕:オオヒメグモの休眠と生活史、林 長閑:生田緑地の谷戸の甲虫、小西正泰:虫・人・本23 |
¥100 |
| 28 |
12月 |
336 |
1991 |
福田晴夫:アサギマダラの季節的移動、坂上昭一・A.W.エブメル:リンネとミツバチ-230年前,リンネはミツバチをどう記述したか-、清水 清:虫を食べる植物、小西正泰:虫・人・本24、1991年度総目次 |
¥100 |
| 29 |
1月 |
337 |
1992 |
田中 誠:明治の子供と昆虫採集、小西正泰:虫・人・本㉕ |
¥100 |
| 29 |
2月 |
338 |
1992 |
坂上昭一ほか:シタバチ ミツバチの華麗ないとこたち①、東 正剛ほか:南極のトビムシ |
¥100 |
| 29 |
4月 |
340 |
1992 |
坂上昭一ほか:シタバチ ミツバチの華麗ないとこたち③、松浦 誠:都市で多発するスズメバチ② |
¥100 |
| 29 |
5月 |
341 |
1992 |
塚本リサほか:ベニツチカメムシの繁殖と給餌、広渡俊哉:ボゴール動物博物館を訪ねて |
¥100 |
| 29 |
7月 |
343 |
1992 |
鈴木信彦:ジャコウアゲハの交尾栓とオスの交尾戦略 |
¥100 |
| 29 |
8月 |
344 |
1992 |
大澤直哉:ナミテントウの生物学① |
¥100 |
| 29 |
10月 |
346 |
1992 |
有田豊:スカシバガの採集と飼育(10ページ) |
¥100 |
| 30 |
2月 |
350 |
1993 |
上田恭一郎:顕微鏡の歴史、小西正泰:虫・人・本38 |
¥100 |
| 30 |
3月 |
351 |
1993 |
板倉泰弘:アズマキシダグモの生活史と婚姻給餌、川口源一:チャタテムシの発音、小西正泰:虫・人・本39 |
¥100 |
| 30 |
4月 |
352 |
1993 |
桐谷圭治・森本信生:日本の外来昆虫、小西正泰:虫・人・本40 |
¥100 |
| 30 |
5月 |
353 |
1993 |
松良俊明:オーストラリアのアリジゴク 巣穴の進化をめぐって(1)、小西正泰:虫・人・本41 |
¥100 |
| 30 |
6月 |
354 |
1993 |
中部水生昆虫研究会:アミメカゲロウはなぜ大発生するのか 成虫の集団羽化と単為生殖①、松良俊明:オーストラリアのアリジゴク 巣穴の進化をめぐって(2)、小西正泰:虫・人・本42 |
¥100 |
| 30 |
7月 |
355 |
1993 |
中部水生昆虫研究会:アミメカゲロウはなぜ大発生するのか 成虫の集団羽化と単為生殖②、小西正泰:虫・人・本43 |
¥100 |
| 30 |
8月 |
356 |
1993 |
岩崎 拓:カマキリに寄生するヤドリバエの生活史、小西正泰:虫・人・本44 |
¥100 |
| 30 |
9月 |
357 |
1993 |
上田哲行:アキアカネの生活史における諸問題1、本田 洋:ソノーラ砂漠の自然と昆虫たち、小西正泰:虫・人・本45 |
¥100 |
| 30 |
10月 |
358 |
1993 |
上田哲行:アキアカネの生活史における諸問題2、岩崎 靖:トガリバガガンボモドキの狩りと交尾、小西正泰:虫・人・本46 |
¥100 |
| 30 |
11月 |
359 |
1993 |
上田哲行:アキアカネの生活史における諸問題3(最終回)、岡田浩明:コオイムシとオオコオイムシの生態と種間競争、田中 誠・松木和雄:松森胤保のトンボ図譜、小西正泰:虫・人・本47 |
¥100 |
| 30 |
12月 |
360 |
1993 |
青木重幸・黒須詩子:ウラジロエゴノキアブラムシの虫こぶと兵隊、小西正泰:虫・人・本48、小西正泰:「虫・人・本」の連載を終わって、1993年度総目次 |
¥100 |
| 31 |
1月 |
361 |
1994 |
日高敏隆:極北の島スピッツベルゲンを訪ねて、栗村康雄:イギリスの昆虫学①収集の時代 |
¥100 |
| 31 |
2月 |
362 |
1994 |
窪田敬士:クサカゲロウの飼育 餌不足に対する反応、栗村康雄:イギリスの昆虫学②科学の時代 |
¥100 |
| 31 |
4月 |
364 |
1994 |
松本和馬:同居するアワフキムシ マツアワフキ幼虫の集合と密度効果、氏家昌行:アカオサムシの飼育 |
¥100 |
| 31 |
5月 |
365 |
1994 |
清水 孝:冷光の男たち 神田左京と宮入慶之助① |
¥100 |
| 31 |
7月 |
367 |
1994 |
長島孝行:シルクの家で暮らす虫 シロアリモドキ、島田公夫:南極で暮らすユスリカの話 その耐寒性について、失敗しないタガメの育て方29ヵ条、清水 孝:冷光の男たち 神田左京と宮入慶之助③ |
¥100 |
| 31 |
8月 |
368 |
1994 |
梅谷献二:中国で食べた昆虫料理、高久 元:甲虫に便乗するダニ |
¥100 |
| 31 |
9月 |
369 |
1994 |
鈴木邦雄:トンボのハネの話、竹田真木生ほか:広い中国でバッタ,コオロギ,キリギリスを追っかけた話① |
¥100 |
| 31 |
11月 |
371 |
1994 |
田中 寛:トノサマバッタの休眠と生活史①、伊藤嘉昭:熱帯・亜熱帯にアシナガバチ社会進化の跡を求めて②、竹田真木生ほか:広い中国でバッタ,コオロギ,キリギリスを追っかけた話③ |
¥100 |
| 31 |
12月 |
372 |
1994 |
田中 寛:トノサマバッタの休眠と生活史②、伊藤嘉昭:熱帯・亜熱帯にアシナガバチ社会進化の跡を求めて③、1994年度総目次 |
¥100 |
| 32 |
1月 |
373 |
1995 |
伊藤嘉昭:熱帯・亜熱帯にアシナガバチ社会進化の跡を求めて④ |
¥100 |
| 32 |
2月 |
374 |
1995 |
佐々木 均:ツェツェバエの吸血源動物、有賀文章:ジガバチ類の生活①ミカドジガバチ、伊藤嘉昭:熱帯・亜熱帯にアシナガバチ社会進化の跡を求めて⑤ |
¥100 |
| 32 |
3月 |
375 |
1995 |
高橋敬一:アルファルファ草地のテントウムシ-ナナホシテントウとナミテントウ- |
¥100 |
| 32 |
4月 |
376 |
1995 |
有賀文章:ジガバチ類の生活②ジガバチ、梁 醒財・森 豊彦:中国と日本のオトシブミ-雲南省と四川省の調査を中心に- |
¥100 |
| 32 |
5月 |
377 |
1995 |
追悼 岩田久二雄先生(坂上昭一:岩田久二雄先生のハチ学、桃井節也:岩田久二雄先生への鎮魂歌、小西正泰:岩田久二雄博士の著書) |
¥100 |
| 32 |
9月 |
381 |
1995 |
矢野修一:イヌガラシの用心棒、巣瀬 司:コアシナガバチの生態② |
¥100 |
| 32 |
10月 |
382 |
1995 |
高須啓志:寄生バチの子殺し、大和田 守:美しい蛾,オキナワルリチラシの飼育から、有賀文章:ジガバチ類の生活⑤クロアナバチ |
¥100 |
| 33 |
1月 |
384 |
1996 |
佐藤宏明:ケニアのタマオシコガネの巣作りと子育て、田中 誠:江戸城に納められた虫たち |
¥100 |
| 33 |
2月 |
385 |
1996 |
鎌田直人:ブナアオシャチホコの大発生と個体群動態 ブナ林の昆虫密度はいかに制御されているか①、有賀文章:ジガバチ類の生活⑥コクロアナバチ |
¥100 |
| 33 |
3月 |
386 |
1996 |
鎌田直人:ブナアオシャチホコの大発生と個体群動態 ブナ林の昆虫密度はいかに制御されているか②、楠本孝幸:(ヤマト)タマムシの採集と飼育 |
¥100 |
| 33 |
4月 |
387 |
1996 |
田中誠二:トノサマバッタの相変異と体色多型(1) |
¥100 |
| 33 |
5月 |
388 |
1996 |
田中誠二:トノサマバッタの相変異と体色多型(2)、鈴木邦雄・上原千春:オトシブミのゆりかごのしくみ①、有賀文章:ジガバチ類の生活⑦アルマンモモアカアナバチ |
¥100 |
| 33 |
6月 |
389 |
1996 |
鈴木邦雄・上原千春:オトシブミのゆりかごのしくみ②、山根爽一:ハラグロビロウドスズメバチの巨大巣を採る その特異な攻撃性の素顔 |
¥100 |
| 33 |
7月 |
390 |
1996 |
小野展嗣:セアカゴケグモ オーストラリアからの招かれざる客 |
¥100 |
| 33 |
8月 |
391 |
1996 |
杉浦直人・郷原匡史:キムネクマバチの天敵 ヒラズゲンセイの生活史、酒井春彦:トゲアリの生活 飼育と野外観察をとおして |
¥100 |
| 33 |
9月 |
392 |
1996 |
芳野未央:立川周二:バリ島の「コオロギ相撲」見聞記、原田哲夫:アメンボ類の翅の長さと生活史 |
¥100 |
| 33 |
12月 |
395 |
1996 |
市川憲平:日本産のコバンムシはなぜヒシに卵を産むのか、1996年度総目次 |
¥100 |
| 34 |
1月 |
396 |
1997 |
森 勇一:虫が語る日本史 昆虫考古学の現場から①、正木進三:コオロギはなぜ秋に鳴くのか、吉松慎一:地中で生活するヤガの話 |
¥100 |
| 34 |
4月 |
399 |
1997 |
山内克典:トビニセハリアリにおける無翅オスの二型、宮下 直:ジョロウグモの網に秘められた意味 |
¥150 |
| 34 |
8月 |
403 |
1997 |
深津武馬:ジャワの高原に謎の兵隊アブラムシを追って(1)、天野和弘:刺さないミツバチをつくる |
¥150 |
| 35 |
1月 |
408 |
1998 |
田中 誠:虫譜にみる江戸の昆虫たち、川那部真:サルノコシカケの中にすむツツキノコムシの世界 |
¥150 |
| 35 |
2月 |
409 |
1998 |
藤山直之・白井洋一:インゲンテントウ-子ども用図鑑から見つかった侵入昆虫-、香取郁夫:モンシロチョウの訪花生態[1]訪花学習性 |
¥150 |
| 35 |
3月 |
410 |
1998 |
杉浦直人:ハナバチはどうやって眠るか、香取郁夫:モンシロチョウの訪花生態[2]人工蜜標に対する訪花活動および送粉効果 |
¥150 |
| 35 |
4月 |
411 |
1998 |
橋本佳明・山根正気:アリを狩るアリ,アリを狩るヒト[1]アジアの軍隊アリ「ヒメサスライアリ」を求めて、後北峰之:アダンの航跡を追うツダナナフシ |
¥150 |
| 35 |
5月 |
412 |
1998 |
井上亜古:オドリバエの求愛給餌、山根正気・橋本佳明:アリを狩るアリ,アリを狩るヒト[2]インベントリーと参照標本コレクション |
¥150 |
| 35 |
9月 |
416 |
1998 |
早川博文:ガゼラエンマコガネの生態と利用 |
¥150 |
| 36 |
1月 |
420 |
1999 |
平田慎一郎:カマキリモドキの幼虫の生活、田中 誠:害虫防除の民俗行事、松香宏隆:僕が見たトリバネアゲハ |
¥150 |
| 36 |
2月 |
421 |
1999 |
巣瀬 司:サクラソウの花粉媒介昆虫 |
¥150 |
| 36 |
3月 |
422 |
1999 |
赤井 弘:巨大な繭を作るアフリカの絹糸昆虫「アナフェ」、野中健一:闘うカブトムシ 北タイのカブトムシ・レスリング、篠原圭三郎:マクラギヤスデの生活 |
¥150 |
| 36 |
4月 |
423 |
1999 |
椿 宜高:翅の色は何を語るか-カワトンボが色づくとき-、神崎亮平:昆虫ロボットの話[1] |
¥150 |
| 36 |
5月 |
424 |
1999 |
工藤起来:巣作りと子育てと-アシナガバチの労力配分-、神崎亮平:昆虫ロボットの話[2] |
¥150 |
| 36 |
6月 |
425 |
1999 |
吉澤和徳:チャタテムシの生物学①、吉田昭広:オオスカシバの透明な翅-微小突起の役割 |
¥150 |
| 36 |
7月 |
426 |
1999 |
吉澤和徳:チャタテムシの生物学②、加藤義臣:ヤママユガの繭が緑色になるしくみ |
¥150 |
| 36 |
8月 |
427 |
1999 |
竹松葉子:シロアリという昆虫 |
¥150 |
| 36 |
9月 |
428 |
1999 |
特集:ハエ
篠永 哲:特集にあたり ハエとは何か、諏訪正明:ハナバエのくらし、ケネス Y.カネシロ:ハワイのショウジョウバエ 種分化と進化、田中 誠:ハエと日本人
防除の歴史と道具、篠永 哲:都市のハエ、大原賢二:ハナアブの生活から、岩佐光啓:放牧地のハエ クロイエバエの生活、大原賢二:日本のシュモクバエ、ほか |
¥400 |
| 36 |
10月 |
429 |
1999 |
村田浩平:野焼きとオオルリシジミ、伊藤文紀:東南アジアのアリのくらし① |
¥150 |
| 36 |
11月 |
430 |
1999 |
小野正人:マルハナバチの飼育方法 |
¥150 |
| 36 |
12月 |
431 |
1999 |
石谷正宇:環境指標としてのゴミムシ、1999年度総目次 |
¥150 |
| 37 |
1月 |
432 |
2000 |
新島渓子:土の中のはたらき者-土壌動物、田中 誠:「採虫指南」に至るまで |
¥150 |
| 37 |
3月 |
434 |
2000 |
花田聡子:カワゲラのドラミング行動、酒井春彦:トゲアリの観察と飼育 |
¥150 |
| 37 |
5月 |
436 |
2000 |
塘 忠顕:アザミウマ類 「蛹」の時期をもつ不完全変態昆虫 |
¥150 |
| 37 |
6月 |
437 |
2000 |
砂原俊彦:竹筒の中の「ウサギとカメ」-ボウフラたちの競争と共存-、曽田貞滋:分子系統で見るオサムシの進化 オオオサムシ亜属は平行進化したのか? |
¥150 |
| 37 |
8月 |
439 |
2000 |
桐谷圭治:世界を席巻する侵入昆虫 |
¥150 |
| 37 |
9月 |
440 |
2000 |
松浦健二:シロアリの卵に擬態する菌、伊藤文紀:東南アジアのアリのくらし③ |
¥150 |
| 37 |
10月 |
441 |
2000 |
野村周平:東村山市下宅部遺跡の昆虫遺体[1]、小西正泰:昆虫学のあゆみ 西洋編 |
¥150 |
| 37 |
11月 |
442 |
2000 |
野村周平:東村山市下宅部遺跡の昆虫遺体[2]、小西正泰:昆虫学のあゆみ 東洋編 |
¥150 |
| 37 |
12月 |
443 |
2000 |
伊藤文紀:東南アジアのアリのくらし④、2000年度総目次 ※終刊号 |
¥200 |